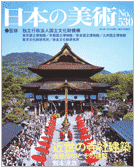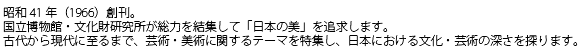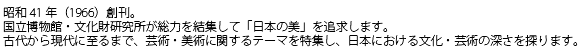
近世、戦国の動乱を経て泰平の世へ向かう時代、人びとの日常には民間信仰、宗教行事が切っても切れないものとして浸透していました。
地域社会の中心となった寺院や神社、巡礼された霊山霊場など、庶民のあつい信仰を集めながら伝えられてきた寺社が、いまも全国各地に護持されています。
数百年にわたり地域を見守った素朴な村堂をはじめ、全国から参詣者を集める大寺など、永らく日本人の心の拠り所であった寺社建築の数々を掲載、その建築構造や来歴を解説します。
特別寄稿に「江戸時代の村堂・小祠」(駒沢大学教授・湯浅隆)を掲載。
文化庁文化財部主任文化財調査官 熊本達哉/執筆
ISBN:978-4-324-08739-8
--------------------------------------
●口絵(カラー16ページ)
●はじめに
・古代の庶民信仰
・中世の庶民信仰
・近世における庶民信仰
・鎌倉新仏教の建築(浄土宗、時宗、浄土真宗、日蓮系諸宗)
●日々の信仰――村のお堂
・村鎮守
・堂と行事
・境界にたつ堂
・茶堂
・特殊な堂
●霊場霊山への参詣
・参詣寺社(鬼子母神信仰、不動信仰、稲荷信仰、金毘羅信仰)
・霊山(熊野、富士山、立山、出羽三山、大山、上毛三山、飯綱山)
・御師
●巡礼と遍路
・百観音霊場(西国三十三所観音霊場、坂東三十三所観音霊場、秩父三十四所観音霊場)
・四国霊場
・霊場のうつし(最上三十三所観音霊場、会津三十三観音霊場、小豆島八十八ヶ所霊場)
・百観音堂と栄螺堂
●おわりに――近世から近代へ
・庶民信仰と近世の寺社建築
・近代へ
●特別寄稿 江戸時代の村堂・小祠
江戸時代に仏や神を祀った建物/村の信仰/『江戸名所図会』に記された村堂・小祠
/駒沢大学教授 湯浅隆
●参考文献
●図版目録