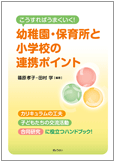平成20年改訂の「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「小学校学習指導要領」では、
幼稚園・保育所と小学校が互いに、子ども同士の交流の機会や、
職員の意見交換・合同研究の機会を設けるなど積極的な連携を図るようにすることという規定が
新たに盛り込まれました。
背景には、幼稚園・保育所での生活から学校生活へとスムーズに移行できず、
心身に変調をきたす児童が出たり学級が荒れたりする、
いわゆる「小1プロブレム」の課題などがあります。
こうした問題を引き起こさないためにも、情報共有や相互理解、合同の研究が必要とされています。
本書では、子どもたちの交流活動、アプローチカリキュラム・スタートカリキュラムの工夫、
合同職員研修など、さまざまな実際の取り組みを紹介しながら、
幼保小連携の課題と推進のためのポイントをまとめています。
就学前後を見通した保育・教育実践に役立つハンドブックです。
目次
1 なぜ幼保小の連携が求められているのか
子どもや社会の現状と課題
幼児期と小学校を円滑に結ぶ
2 幼保小連携を進めるポイント
5歳児から小学校1年生の子どもの成長
5歳児から小学校1年生の子どもの学び
豊かな幼保小連携を実現する方策
3 こうすればうまくいく!幼保小連携
幼児期の教育の事例(5歳児前期の学び/5歳児後期の学び)
小学校教育の事例(入学当初の学び/小学校1年生の学び)
互恵性を大切にした交流活動(生活科での交流活動/特別活動での交流活動)
4 こうして進める幼保小連携
こうしてつなぐ幼保小連携(指導力を高める研修1・2/要録でつなぐ幼保小連携1・2/連携をつなぐ体制整備)
こうして支える幼保小連携(教育委員会のサポート/環境を生かした連携/家庭との連携)
編著者紹介(肩書は発刊当時、敬称略)
篠原孝子…しのはら・たかこ/文部科学省初等中等教育局幼児教育課教科調査官
田村学…たむら・まなぶ/文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官